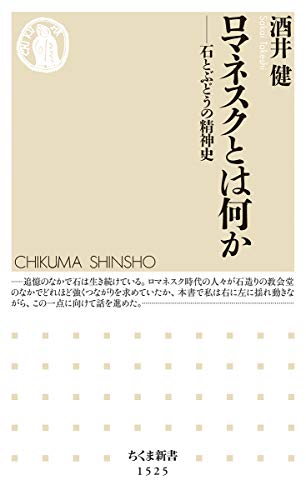酒井健著『ロマネスクとは何かー石とぶどうの精神史』(ちくま新書)
バチカンのサン・ピエトロ大聖堂を一度だけ訪れたことがあります。
聖堂内にあるベルニーニの天蓋。
ねじれた柱が印象的でした。
しかしよく考えてみると、バロックの巨人ベルニーニ本来の建築語法とは異質な構築物。
なぜこんな造形がここに示されているのか。
その答えが本書で詳しく述べられています。
ロマネスクという言葉がウィリアム・ガン、シャルル・ド・ジェルヴィルという二人の好古家によって生み出されたことを紹介しつつ、著者はそれが「古代ローマに似ているようで異なる、似て非なるという意味」(P.17)と再定義しています。
独特の尖塔アーチに代表されるゴシックが比較的わかりやすい様式であるのに対し、ロマネスクには、どこか捉え所がない曖昧さがつきまとっているようにも感じられます。
先んじる古代ローマの、ある意味普遍的な均整を重んじる様式と、垂直に天を志向する壮麗なゴシック様式の間にあって、ロマネスク様式は質朴さとグロテスクさを合わせ持ち、一括りにできない多様性を持っています。
そこが魅力であり、曖昧さゆえにわかりにくい面をもっているともいえそうです。
著者の「似て非なる」という説明は一時代を画した様式に使う言葉としてはやや消極的かもしれません。
しかし、逆に一言で言い表せない、多面的なロマネスクの容貌を端的に示しているとも感じます。
本書が主に対象としている時代は950年から1150年。
中世中期です。
しかし、ロマネスクの淵源として著者は、古代ローマ末期、コンスタンティヌス大帝の時代にまで遡って説明をはじめます。
「ベルニーニの天蓋」がなぜ、ねじれた柱で構成されているのか。
柱の正体は「ぶどうの木」です。
313年のミラノ勅令でキリスト教を公認した大帝は、サン・ピエトロ大聖堂の起源であるバシリカの建設を指示。
そこでかけられた天蓋に葡萄の木が用いられたのだそうです。
ベルニーニはその伝統をふまえて天蓋を作りました。
葡萄はすなわちバッカス信仰、異教のディオニソスにつながります。
著者はロマネスクを「つなげるもの」と印象的に語ります。
何と何をつなげるのか。
それは一神教であるキリスト教と、それが異教としたギリシア・ローマの神々の世界。
あるいは、形相(エイドス)と、それを踏み越えて湧き出すような物質的な力。
この「つなげるもの」という概念は日本人から見るとわかりやすいかもしれません。
日本では仏教と土着の神々信仰が、明確かつ直接的に神仏習合として形を成した例があります。
ロマネスクはここまで露骨ではないにせよ、「黒いマリア」や、教会の回廊列柱とティンパヌム(タンパン)等に示された動植物・怪物などに、キリスト教とは関係のない、見ようによってはいかがわしい意匠がふんだんに盛り込まれています。
「ローマ的でありながらローマ的ではないという曖昧な中世ロマネスクのキリスト教文化は、パウロの峻厳さおよびその背後にある地中海都市文明と、無定形なガラテアの人々およびその背後のケルトをはじめゲルマンなど西欧の古層を形成した人々(ジェルヴィルの言い方では「われわれの粗野な先祖たち」)の文明とのあいだのさまよいとみなすことができる。この両極を肯定しながら、その間を揺れ動いて様々な混交を生み出したのがロマネスクなのだ。」(P.77〜78)
本書ではロマネスクを美術様式として説明するだけではなく、その背景としての思想、宗教、政治文化の面を含めて多角的に追っています。
逆にいうと、美術史の中でみたロマネスクに関しては限定的な内容にとどまっているとも言えるので、そこに期待すると物足りない印象を受けるかもしれません。
例えば、ロマネスク建築といえば必ず例に出される「プロヴァンスの三姉妹」(ル・トロネ、セナンク、シルヴァカンヌの三修道院)にはふれられていません。
ただ、この方面には別の専門書がたくさんありますから、本書に全てを求める必要はないとは思います。
美術面はともかく、「ロマネスクを生きた人々」(第3部)のような中世人たちを描いた記述がたいそう面白い本です。
澁澤龍彦に影響を与えたロドゥルフス・グラベルの「幻視」、その緻密な批判精神が逆にクリュニー修道会にみられるロマネスクの豊穣さを描き出してしまうシトー派の僧、クレルヴォーのベルナルドゥス。
古代ローマの遺跡に仮託しながら「哀歌」を詠んだラヴァルダンのヒルデベルトゥス。
いずれも一筋縄ではいかないロマネスク人の魅力に溢れています。
もちろん、著者は単純にロマネスク讃歌を本書で歌い上げているわけではなく、凄惨な虐殺や、レコンキスタの中で繰り広げられた同族同志の血生臭い争いにもふれています。
周知の通り酒井健はバタイユ研究で名をなした人でもあるので、本書終盤でしっかり「蕩尽」の概念を持ち出してロマネスク時代に行われた「成果不明の集団祈祷や教会堂建築」(P.251)を説明してもいます。
死後の救済を求める切実苛烈な信仰の力と、自然を畏敬しながらも時に淫らさをも厭わず生を謳歌しようとする力。
その両面がないまぜとなって様々な美や文化を生み出したロマネスク。
どちらに偏ることもなくまさに両極をつなぐように書かれた本書は結果として新書版にしてはかなり豊かな情報量をもっています。
読み応えがありました。