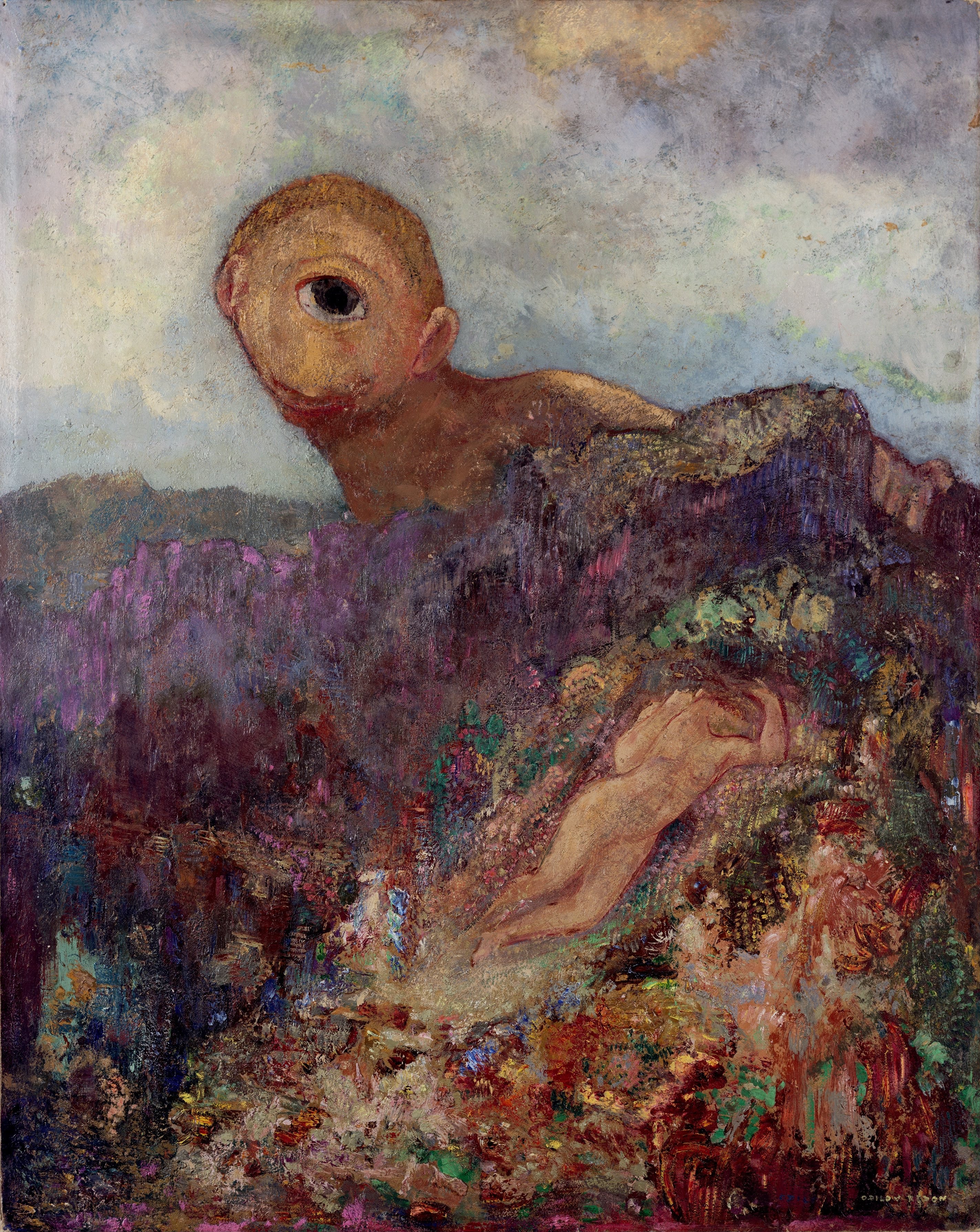小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌(レクイエム)
■2021年8月7日〜9月26日
■京都文化博物館
平塚市美術館の現館長、草薙奈津子によれば、アジア太平洋戦争に最も早く従軍した日本画家が小早川秋聲なのだそうです(中公新書『日本画の歴史 現代篇』P.41)。
明治以降における日本画の歴史を扱った上下2巻にわたる新書の中で、草薙が秋聲について記述しているのはこの「最初の従軍画家」とする三行あまりのみ。
その他の画業について語られている箇所はありません。
私自身、「國之楯」が醸すインパクトがあまりにも強かったために、戦争画の人、というカテゴリーにはめこんで、みてしまってきた画家。
しかし、初企画という今回の大規模回顧展を観ると、そんな印象が一変しました。
秋聲ほどその人生と画風がリンクしている人も珍しいと思います。
初めに弟子入りした谷口香嶠は円山・四条派、幸野楳嶺門下の四天王の一人です。
歴史画を得意とし有職故実に通暁していたという師匠香嶠による手ほどきの跡が、那須与一や楠木正成親子を描いた初期の作品にはっきりみてとれます。
次いで師事した山元春挙も円山・四条派の流れを汲む、こちらも京都画壇の重鎮。
人物画主体の香嶠に対し、春挙はどちらかと言えば山水、風景画の人として知られています。
「旅する画家」であった秋聲は、登山や写真を好んだという春挙と特に波長があったのでしょう。
旅先の風景を写しとった秋聲の絵にはスナップ写真のようなさりげなさと繊細な色調表現が同居していて、春挙の影響が感得されます。
人物表現、景物表現を円山・四条派の本流から受けつぎながら、国内にとどまらず中国からヨーロッパへと旺盛に旅路を駆けた秋聲の画題は伝統的な日本画の枠にとどまりません。
旅の情景を写すだけではなく、「長崎へ航く」ではオランダの港から日本に向かう船とそれを見送る人々の背中を取り合わせています。
イマジネーションの跳躍が色調にまで移ったような爽快でモダンな印象すら与えてくれる傑作。
国粋戦争画の人というイメージはこの一枚で吹き飛んでしまいます。
代表作の一つ「愷陣」は、画面いっぱいに描かれた馬の大胆な構図に驚きますが、細部まで緻密に描画された花々や馬具、毛並みの表現には京都画壇伝統の技量が注ぎ込まれています。
凱旋した武人ではなく、あえてその人を乗せてきた馬だけを豪奢なまでに寿ぐ秋聲の視線は、単純な戦闘賛歌の対極を照射しています。
大正後期の作という「追分物語」ではアイヌの女性らしい人物の異様な表情が印象的。
今年話題になった「あやしい絵」展に飾られたとしても不思議ではないグロテスクさが大きな画像いっぱいに広がります。
この頃の京都は国画創作協会の全盛期でもあり、大正デカダンの空気を秋聲も吸い込んでいたらしいことが想像されます。
師匠筋からの伝統を意識しつつも画題画風、両面で新しさを取り込む好奇心の高さがこの画家からは強く感じられます。
日露戦争への出征、世界一周に近い旅、常に動き回る身軽さもこの好奇心が原動力だったのでしょう。
旅する機動性に加え、秋聲を特徴づけるもう一つの点は、真宗大谷派の僧籍を持っていたということです。
仏教を題材とした作品が数多くみられますが、超越的宗教画よりどこかとぼけた味のする禅僧や仙人などを描いた作品の比率が高いようです。
社会的最下層にいた人々を多く門徒として迎えた東本願寺系の人らしく気取った仏画はほとんど見られません。
他方で東本願寺は皇室とも縁が深いことで知られています。
「薫風」と題された豪華な金屏風は法嗣大谷光暢と久邇宮智子女王の婚姻にあたって作成された作品。
画家としての実力に加えて宗派内の名望もそれなりに得ていたからこその発注なのでしょう。
元々、秋聲が比較的早い時期(1937年)に戦地へ向かったのも、東本願寺から従軍慰問使として嘱託されたためでした。
日露戦争軍属経験者かつ僧侶。
そして「旅する画家」。
真宗大谷派としては秋聲ほど慰問使として相応しい人物はいなかったのだと思われます。
秋聲による人物描写は写実性よりもキャラクター重視がされています。
彼の描く聖徳太子や西行は切長の目がどこか日本人離れした雰囲気をもっているように感じます。
実際の人物を写すというより、想念から生み出された顔。
これは秋聲の戦争画において、正面からとらえた写実的な兵士の画像がほとんどないことと関係しているようにも思えます。
代表作「御旗」で描かれている兵士は後ろ姿。
「國之楯」では顔に日章旗が被されています。
兵士の顔は、秋聲にとっては「描ききる」とどこか「嘘」が見えてしまう対象だったのかもしれません。
表装への趣向に好奇心の燻りを維持したらしい秋聲ですが、戦後はほとんど忘却された画家となってしまいました。
復権は1995年「芸術新潮」で「國之楯」が取り上げられてからだそうですが、このことが皮肉にも「戦争画の人」というイメージの固着につながり、軍部にその受け取りを拒否されたエピソードがかえって余計な鑑賞バイアスを観る者に与えてしまっているようにも感じます。
本格的な小早川秋聲のリバイバルはこの回顧展以降、ということになりそうです。