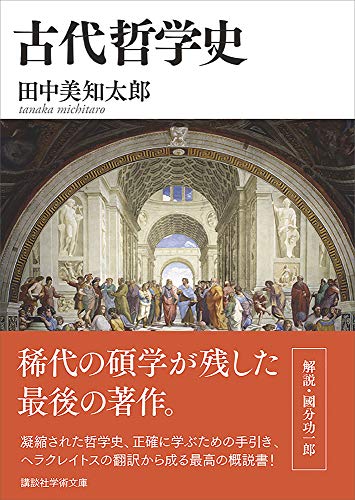田中美知太郎著『古代哲学史』(講談社学術文庫)を読んでみました。
「万物の始原は水である。」
誰しもこの言葉が間違っていると認識しているのに、タレスが、なぜ「最初の哲学者」として今も哲学史の冒頭に登場するのか。
そして、「水」や「空気」など、四大元素の流転説を飛び越えて、唐突ともいえる「アトム」の概念がどうして生じたのか。
わかっていたようでいて、いざ頭の中でギリシア哲学史の、その始まりからの流れをきちんと想起しようとすると、途中で躓いてしまいがちです。
著者本人が「筋が通っている」(本書「あとがき」より)と自賛している本書の論考を読むと、なるほどすっきりと古代哲学史の流れが脳内で再整理されるように感じました。
文庫では3部構成がとられています。
第1部は「西洋古代哲学史」(1949)と「古代アトム論の成立」(1948)。
第2部は「古代哲学I」(1963)と「古代哲学II」(1949)。
第3部は「ヘラクレトスの言葉」(1965)。
この内、第2部「古代哲学II」は初学研究者向けの参考文献を紹介した、いわば高等なガイドブック的文章。
第3部は著者によるヘラクレイトスの言葉とされる文言への注釈集です。
したがって、この文庫のタイトルである『古代哲学史』にそのまま合致する部分は「西洋哲学史」「古代アトム論の成立」「古代哲学I」の前半3論考ということになります。
全体では300ページあまりのボリュームがあるのですが、この3つの部分だけなら120ページくらい。
しかも、いずれもタレスからアリストテレスあたりまでのギリシア哲学の流れをトレースしているので内容的に重複する部分がかなりあります。
ただ、それぞれに語り口や焦点のあて方が微妙に違うのでダブリ感は不思議とさほど覚えません。
タレスを哲学史のはじめにおいたのは、他ならない、アリストテレスです。
著者はそれをふまえた上で、このイオニアの自然学者タレスの思想が、「はじめに水ありき」というような太古の神話的発想といかに別次元のものであったかを紹介しています。
問題は「水」ではなく、あるものを生成と分解の「もと」として設定した考え方そのものにあるのです。
このタレスの発想によって、初めて「現にものは何から成っており、ものは分解すれば何になるかを、めいめい自分で考えてみることができる」(P.20)ようになったと著者は明快に「最初の哲学者」の業績を定義しています。
次いでヘラクレイトスが登場します。
俗に「万物は流転する」と説いた人として知られていますが、著者は彼の本質的思考をもっと深く鋭くえぐっています。
"ヘラクレイトスは、火が空気になり、空気が水となり、水が土になるという、この生成変化において、単なる生成だけでなく、同時に消滅をも見ようとする。"(P.24)
万物流転の思考には「生成と消滅」「万物一体」の意味が組み合わされていて、それこそヘラクレイトスの「真骨頂」だと著者は指摘しています。
なお第3部の「ヘラクレイトスの言葉」では直接、彼の「生成と消滅」を聞くことができます。
タレスからヘラクレイトスへと続くイオニア派の哲学は、エレア派パルメニデスの「あるものはある。ないものはない。」という峻厳な論によって危機を迎え、やがて、レウキッポス等によるアトム論が立ち上がってきます。
「空」や「無」といった概念をどう扱うか、経験か論理か。
その後の哲学史の主要なテーマがソクラテス以前にすでに出揃っていたことが特に「古代アトム論の成立」において、これ以上ないくらい平易に説明されています。
アリストテレスのいう「エイドス」がプラトンの「イデア」とどう違うのか。
「アリストテレスの形相・素材による自然の説明」は「プラトンのこの意欲的な自然把握から、その強烈な意志を引き去った残物のようなもの」と、かなりアリストテレスを突き放したような言い方をしています。(P.114 國分功一郎の解説より)
しかし、なんとなく、言われてみるとこの「イデアとエイドス」の関係性についての説明が感覚的にしっくりくるようにも思えてきます。
付録ともいうべき第3部「ヘラクレイトスの言葉」では現在にも通用する警句めいた文章をいくつもみることができます。例えば以下のような。
"予想しなければ、予想外のものは見出せないであろう。それはそのままでは捉え難く、見出し難いものものなのだから"(P.236)
総じて無駄を省いた簡潔な言葉で説明されている哲学史概説ですが、読めば読むほど深みが増す。
そんな論考でした。